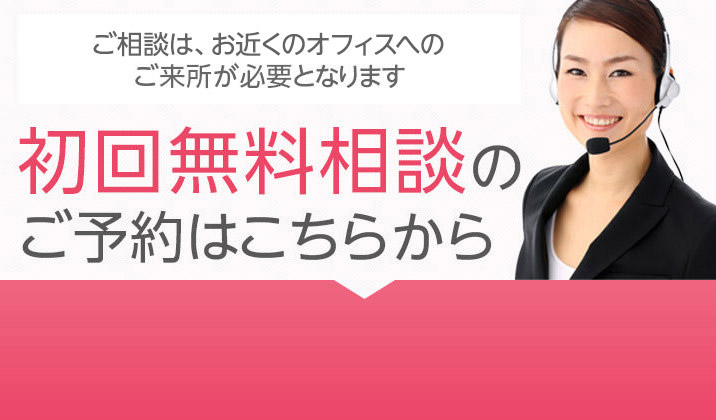離婚時に年金分割をした後に妻が再婚。妻の死後、年金の行方はどうなる?
- 離婚
- 離婚
- 年金分割
- 再婚

離婚率が全国トップの沖縄では、年金分割は決して人ごとではありません。離婚するときには年金分割の手続きをすると、(主に)妻が厚生年金に加入していなくても(主に)夫が受給する年金を妻が受け取れるようになります。
では、離婚時に年金分割をした夫婦のどちらかが再婚した場合、分割された年金はどうなるのでしょうか。また、どちらかが死亡したら支給は打ち切りになるのでしょうか。本記事では、年金分割をした後、再婚したり死亡したりした場合に年金の行方がどうなるのかについて解説します。


1、年金分割制度とは
離婚するときには、年金事務所に請求を行うことで相手方に支払われる老齢厚生年金の一部を分けてもらうことができ、この制度を「年金分割制度」と言います。
年金分割の対象となるのは、公的年金のうち厚生年金と旧共済年金のみです(共済年金は平成27年10月に厚生年金に一元化)。
年金制度は以下のように3階建ての構造になっています。
2階:厚生年金及び旧共済年金
1階:国民年金
このうち、分割の対象となるのは2階建ての部分のみとなります。そのため、配偶者が自営業だった場合で国民年金にしか加入していなかった場合には、年金分割はできません。
なお、原則として受給資格期間が10年以上ある場合には65歳から年金を受け取ることができます。
-
(1)年金分割の対象期間
離婚時に年金分割ができるのは、婚姻中に年金保険料を納めていた期間のみです。婚姻期間に納めた保険料の記録を分割することになります。また、年金分割は平成19年4月1日に施行された制度なので、平成19年3月までに離婚した夫婦には適用されません。
-
(2)年金分割を受けるために必要な条件
年金分割を受けるには、国民年金保険料を納付していた期間と納付免除を受けていた期間が合わせて10年以上であることが必要です。必要年数に達していなければ、分割された年金を受け取ることはできません。
-
(3)年金分割を受けたときに年金が減ることがある
年金分割を受けると、たいていの場合受け取れる年金額が増額しますが、ある条件に当てはまる方の場合は逆に年金額が減ることがあります。
それは、振替加算がプラスされている老齢基礎年金を受給している方が、年金分割に伴い離婚時みなし被保険者期間を含めた厚生年金保険の被保険者期間が240月以上になった場合です。
振替加算とは、老齢厚生年金の受給している者の配偶者が65歳未満のときに老齢厚生年金に上乗せされる「加給年金」が打ち切られた後、配偶者の老齢基礎年金に上乗せされるものです。
年金分割を受けた場合、上記の条件にあてはまると振替加算の支給がストップするため、受け取れる年金の金額が減ってしまうことに注意しましょう。 -
(4)年金分割の請求期限に注意
年金分割を請求できるのは、以下のいずれの日の翌日から起算して2年以内です。
- 離婚をした日
- 婚姻の取り消しをした日
- 事実婚関係にある人が国民年金第3号被保険者資格を喪失し、事実婚関係が解消したと認められる日
ただし、以下の条件に該当する場合は、該当する日の翌日から起算して1ヶ月以内であれば請求が可能です。
- 離婚から2年を経過するまでに調停または審判の申立てをして、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の1ヶ月以内に調停が成立または審判が確定した。
- 按分割合に関する附帯処分を求める申立てをして、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の1ヶ月以内に按分割合を定めた判決が確定または和解が成立した。
2、合意分割制度とは
年金分割方法には、合意分割制度と3号分割制度の2種類があります。
合意分割制度とは、婚姻期間中に加入していた厚生年金記録を、2人で合意した按分割合に基づき分割する制度です。
合意分割のメリットは、結婚してから離婚するまでのすべての期間に加入していた厚生年金の保険料納付記録が対象になることです。
按分割合は当事者同士で2分の1を限度として自由に決めることができますが、按分割合について夫婦間の話し合いで合意できない場合は、夫婦のどちらか一方の裁判所に調停または審判を申し立てて、裁判所を介して決めることもできます。
なお、調停や審判、裁判手続きは、家庭裁判所にて行われます。那覇市内の主な家庭裁判所は以下です。詳細や最新情報は、裁判所ホームページをご確認ください。
裁判所ウェブサイト(管内の裁判所の所在地)
〒900-8603
沖縄県那覇市樋川1-14-10
夫婦間の協議によって按分割合を定めた場合、合意内容を記した公正証書の謄本や公証人の認証を受けた書面が手続きに必要となります。夫婦間で合意できたら、必ず合意書を作って公証役場へ持参して手続きを行うのを忘れないようにしましょう。あるいは、夫婦2人で合意書を年金事務所に持参するか、年金事務所においてある専用の用紙を使って二人で合意書を作成しても問題ありません。
その後、夫婦のどちらか一方が「標準報酬改定請求書」と呼ばれる書類に必要事項を記入し、必要書類を添付して年金事務所に提出します。受理されると標準報酬改定通知書が夫婦双方に届きます。
3、3号分割制度とは
3号分割制度とは、専業主婦(夫)など厚生年金保険加入者の扶養に入っていた方が、相手方の保険料納付期間を2分の1ずつ相手方と分け合う制度です。厚生年金保険加入者の被扶養者は年金加入者の分類上「第3号被保険者」と呼ばれるため、このような名称になっています。
3号分割制度は、離婚後に年金分割を受ける側が年金事務所に請求すれば、年金分割をする側の合意がなくとも年金記録を分割してもらえる点がメリットです。結婚期間中に合意分割の対象となる期間と3号分割の対象となる期間が混在していれば、合意分割にもとづく請求が行われた時に、3号分割についても請求があったものとみなされます。そのため、この場合も合意は不要となります。
ただし、第3号被保険者でも、3号分割制度が始まる前の平成20年3月31日以前の厚生年金保険加入期間については3号分割ができず、合意分割となることに注意が必要です。
4、一方が再婚or死亡したら年金分割の支給に影響はある?
昨今では再婚する方も増えているため、年金分割を行った夫婦のうち、どちらか一方が数年後に再婚することは十分にありえる話です。また、いずれはどちらかが先に亡くなることも考えられます。その際、分割した年金の支給に影響はあるのでしょうか。
-
(1)再婚しても年金の支給には影響ない
年金分割する側が再婚して配偶者や子どもを扶養するようになったとしても、年金分割を受けた側に分割された年金が支給されないことはなく、支給金額も減ることはありません。
また、逆に年金分割を受けた側が再婚して再婚相手の扶養に入ったとしても、年金分割はそのまま予定通り行われます。 -
(2)年金分割した方が再婚後に死亡した場合
年金分割する側が再婚後に死亡した場合、再婚相手の受け取れる遺族厚生年金の金額は減ってしまいます。なぜなら、死亡した配偶者の厚生年金保険加入期間とその間の報酬で計算された報酬比例部分の額がすでに分割されているからです。
もともと遺族年金はその報酬比例部分の額の4分の3について支給を受けることができますが、再婚相手が受けられるのは4分の3よりも少ない金額になります。 -
(3)年金分割を受けた方が再婚後に死亡した場合
逆に、年金分割を受けた側が再婚後に死亡した場合は、分割した年金は年金分割をうけた側の再婚相手やその子供のもとに遺族年金として入ることになります。なぜなら、再婚相手は遺族年金の支給要件である老齢厚生年金の受給権者の死亡に該当するからです。
そのため、理不尽に思う方も多いかもしれませんが、年金分割をした側にとっては、見ず知らずの相手に自分の年金が渡ることになるのです。
5、年金分割で誤解されやすいポイント
仕組みや手続きが複雑な年金分割制度ですが、この制度には誤解されやすいポイントがいくつかあります。その代表的なものを以下3つあげて解説します。
-
(1)専業主婦(夫)は必ず夫(妻)の年金を半分もらえる
専業主婦(夫)なら、必ず別れた夫(妻)に支給される年金を半分もらえると思ってる方は多いのではないでしょうか。しかし、平成20年4月1日以前に結婚したカップルの場合は、結婚した日から平成20年3月31日までの期間については、どちらかが専業主婦(夫)であっても合意分割が適用されます。
合意分割では必ずしも按分割合が2分の1ずつとなるとは限らないため、専業主婦(夫)は必ず相手方の年金を必ず半分もらえるわけではありません。また、分割するのは年金の支給額ではなく、あくまでも保険料の納付記録であることも覚えておきましょう。 -
(2)年金分割する方が65歳以上なら分割を受ける方もすぐ年金を受け取れる
年金分割する側は、65歳以上になれば年金を受け取れるようになりますが、そのときに分割を受ける側が65歳に達していなければ、いくら条件を満たしていても分割された年金を受け取ることはできません。
また、年金分割を受けるには、離婚した日等の翌日から2年以内に年金事務所で所定の手続きをすることが必要です。按分割合について合意できたからといって、自動的に支給が開始されるわけではないことに注意しましょう。 -
(3)再婚・死亡したら支給が終了する
年金分割する側が死亡したり、分割を受ける側が再婚したりすると、自動的に分割された年金の支給が終了してしまうというイメージを持つ方は決して少なくありません。
しかし、年金分割する側が死亡、もしくは分割を受ける側が再婚しても、年金の支給には何ら影響はありません。再婚すると受給権がなくなってしまう遺族年金とはまた違った制度なので、混同しないようにしましょう。
お問い合わせください。
6、まとめ
年金は老後の暮らしを支えるものです。そのため、離婚時に年金分割をした場合、それぞれの支給金額がどうなるのかを知ることも重要ですが、どちらか一方が再婚したり死亡したりしたときにその年金がどうなるのかも気になるところではないでしょうか。
ベリーベスト法律事務所では、離婚時の年金分割について相談を承っております。年金分割を利用される方が多いことは事実ですが、中には財産分与を多くする代わりに年金分割はしないという決断をするケースもあります。
年金分割制度は非常に複雑な仕組みになっているため、年金分割を検討される際には、ベリーベスト法律事務所 那覇オフィスまでお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています