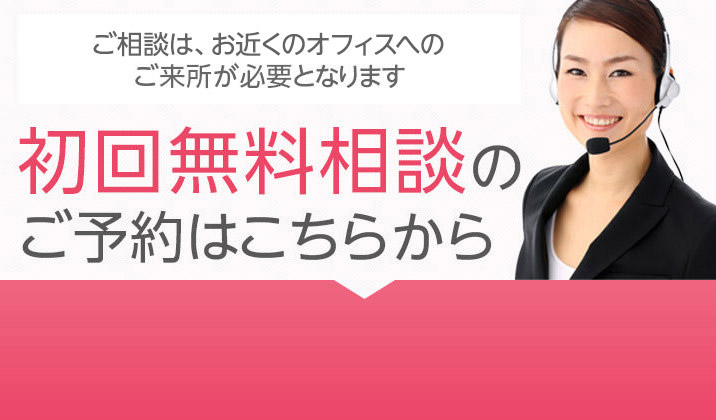離婚をしない場合も婚姻費用の支払いは必要? 婚姻費用の考え方と注意点
- その他
- 婚姻費用
- 離婚しない

那覇市が公表している統計書によると、令和5年中の離婚件数は722組でした。
離婚の危機が訪れたときには、お互いに冷静になる時間を作るために別居を選択する夫婦もいます。しかし別々に生活することで、金銭的な問題がでてきます。
別居期間中であっても離婚が成立するまでは、収入の多い夫婦の一方は他方に婚姻費用を支払って相手の生活を支える義務があるとされます。
しかし、離婚前提の別居であったはずなのに離婚を拒まれ、婚姻費用を請求された場合は、「本当に支払い義務はあるのか?」「いつまで支払わなければならないのか?」といった疑問が生じることでしょう。
本コラムでは、離婚しない場合にも配偶者に対して婚姻費用を支払い続ける必要があるのか、ベリーベスト法律事務所 那覇オフィスの弁護士が解説します。


1、そもそも婚姻費用とは?
婚姻費用とは、夫婦が結婚生活を送るうえで必要な生活費のことです。
婚姻費用には、衣食住に関わる日常の生活費や子どもの養育費、交際費、医療費などが含まれると考えられています。
おおまかにいえば、夫婦や子どもが生活を送るために必要な費用、といえるでしょう。
婚姻費用の金額は夫婦で決めることができますが、決める際の目安になるのが婚姻費用の算定表です。
たとえば専業主婦の妻が自宅に残り、収入のある夫がマンションなどを借りて別居することになったとします。このようなケースでは、夫が妻に生活費を渡さなければ、妻は当面の生活にも困ることになるでしょう。
夫婦には、お互いを扶養し同程度の生活水準で生活する法律上の権利・義務があるとされています。そのため、例に挙げたようなケースでは、別居したとしても離婚が成立するまでは収入の多い夫が専業主婦である妻に、婚姻費用として生活費を支払わなければならないとされています。
2、離婚を拒む配偶者に婚姻費用を支払う必要はある
婚姻費用は、夫婦の扶養義務を根拠とします。そのため別居していても、法律上夫婦である限り扶養義務があります。
つまり、離婚の意思の有無に関わらず、収入の多い側が少ない側に、婚姻費用を支払い続けなければなりません。
たとえば、離婚を前提として別居したはずなのに、妻(夫)が離婚することを拒み別居を続けているような場合にも、婚姻費用は支払い続ける必要があります。
婚姻費用を配偶者に支払う必要がなくなるのは、「離婚が成立したとき」です。
なお、婚姻費用を受け取る側に別居の原因があったような場合でも、婚姻費用を支払う必要はあります。裁判所の調停を利用し婚姻費用を算定する場合には、別居事由が考慮される場合もあります。
また、調停や審判を通して、支払うことが確定しているにもかかわらず拒み続ければ、裁判所に強制執行を申し立てられるおそれがあるでしょう。強制執行が認められると、給与などの財産を差し押さえられてしまいます。
強制執行認諾文言付きの公正証書を作成している場合も、強制執行を申し立てられる可能性があるため、注意が必要です。
お問い合わせください。
3、婚姻費用の目安は?
婚姻費用の金額については、裁判所がホームページなどで公表する「算定表」を基準にすることができます。この「算定表」は、家庭裁判所の調停や審判で婚姻費用を算定する場合に参考にされているものです。
なお、ベリーベスト法律事務所では、最高裁判所が公表している婚姻費用算定表をもとにした、簡単に婚姻費用を算定できる「婚姻費用計算ツール」をご用意しています。
では、同ツールにもとづいて、どの程度の婚姻費用が必要になるのか具体例をみていきましょう。
今回は、「年収500万」の会社員と「年収800万円」の会社員を例に、別居する専業主婦(主夫)の配偶者(子どもと同居)がいるケースで算出します。
-
例① 子どもが1人(14歳)いるとき
- ●年収500万円の会社員の場合
- 婚姻費用の目安は「10~12万円」です。
- ●年収800万円の会社員
- 婚姻費用の目安は、「16~18万円」です。
-
例② 子どもが2人(15歳と10歳)いるとき
- ●年収500万円の会社員の場合
- 婚姻費用の目安は「12~14万円」です。
- ●年収800万円の会社員
- 婚姻費用の目安は「18~20万円」です。
このように、年収や子どもの人数によって、婚姻費用の目安も変わることがわかります。
婚姻費用計算ツールでは、子どもが3人いるケースまで簡単に算出ができますので、ぜひご利用ください。
4、婚姻費用の話し合いがうまくいかないときの対処法
婚姻費用の金額について、夫婦の話し合いで合意できないときには、次のような対処法を検討するとよいでしょう。
-
(1)裁判所の調停や審判で解決を図る
婚姻費用の分担について、話し合いで合意できないような場合には、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求の調停」を申し立てて解決を図る方法があります。
調停では、調停委員が当事者双方の言い分を聞き、夫婦双方の資産や収入、支出、子どもの有無や年齢などが考慮されたうえで解決策を提示したりアドバイスしたりして、合意をめざします。
調停で合意ができないときは、調停不成立となり自動的に審判手続きが開始されることになります。審判では、裁判官の判断によって婚姻費用額が決定します。
なお、必ずしも調停を申し立ててから、審判を申し立てる必要があるわけではありません。結論をいそぐ理由があるときなどには、調停を省略して審判を申し立てる方法もあります。しかし、審判の場合は最終的には裁判官の判断によって結論が出るため、ご自身にとって望まない結果になる可能性があることを理解しておきましょう。 -
(2)弁護士に相談する
婚姻費用について夫婦の話し合いがうまくいかないときには、弁護士に相談する方法もあります。
弁護士は代理人になることができるため、直接配偶者と顔を合わせなくても話し合いを進めることができます。弁護士が介入することで、話し合いのみで解決につながるケースも少なくありません。
また、調停や審判に発展した場合は、書類の準備など手続きの一切を任せることができるだけではなく、裁判所に認められやすい主張や証拠を熟知している点も大きなメリットといえるでしょう。
なお、婚姻費用だけではなく、離婚成立に向けた話し合いや、財産分与、慰謝料などのお金の問題、親権や面会交流といった子どもの問題など、さまざまな事柄についても弁護士に相談することが可能です。
弁護士は、状況に応じた解決案を提示しつつ、納得いく結果になるよう最後まで徹底的にサポートします。
5、まとめ
離婚はせずに別居している場合でも、婚姻費用を支払う必要はあります。たとえ、別居期間が長くなったとしても、法律上の夫婦である以上、収入が多い方が少ない方に婚姻費用を支払わなければいけません。
婚姻費用の金額に納得できない場合や、調停や審判を提起され対応に苦慮している場合、離婚を成立させたいなどのお悩みを抱えている場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
ベリーベスト法律事務所 那覇オフィスには、婚姻費用のトラブルをはじめ、離婚問題の対応実績が豊富な弁護士が在籍しています。お悩みを解決できるよう全力でサポートしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています