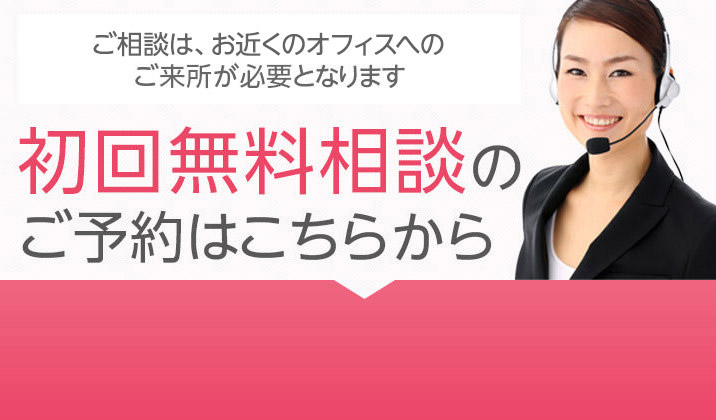もし離婚裁判を申し立てられたら? 早期解決のために知っておくべきこと
- 離婚
- 離婚
- 裁判
- 調停

厚生労働省が公表している「令和5年人口動態統計」によると、沖縄県における令和5年の離婚件数は3170件と、前年より83件増加しました。
結婚をして夫婦そろって幸せな家庭を築いていたのに、いつの間にかすれ違いを起こし、大変な離婚劇に巻き込まれてしまうという方は意外と多いのです。
本コラムでは、裁判離婚にかかる費用や期間、早期解決のポイントについて、ベリーベスト法律事務所 那覇オフィスの弁護士が解説します。


1、裁判で離婚するには法律上の離婚原因が必要
実は、裁判で離婚を争うことになった場合、絶対に離婚できるとはいえません。裁判離婚の場合、まず「民法上の離婚原因が存在するのか」という基準から離婚を認めるか否かを判断するためです。もし、法律上の離婚原因が存在しなかった場合には、離婚は認められません。
以下で民法上の裁判原因について解説します。
-
(1)裁判離婚で認められる主な離婚原因
民法上の離婚事由については、770条1項に「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。」と規定し、離婚事由としては、以下の5つを掲げています。
① 配偶者に不貞な行為があったとき
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき
③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
不貞行為(①)とは、婚姻中の配偶者の不倫行為などを指します。
悪意で遺棄(②)とは、生活費を支払わないことや家を出て行ってしまったことなどを意味します。
生死が3年以上明らかでないとき(③)や強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(④)は、婚姻の継続が難しいと考えられるため、離婚が認められます。
また、これら以外でも、DVや長期間の別居がある場合など婚姻を継続できない決定的な事由が認められる場合(⑤)には、離婚が認められます。離婚の理由として、かなり多くの人が挙げる「性格の不一致」については、夫婦関係が修復不可能なまでに破綻していると言える場合には、⑤として認められます。
不倫、別居、DV、性格の不一致など一般的な離婚理由はほとんど離婚原因となるため、後は実際に離婚理由があったことを証明できるかの問題となります。 -
(2)離婚裁判をすれば必ず離婚が成立するとも限らない
離婚成立には、法律上の離婚原因があるかどうかだけではなく、当事者双方の主張の正当性や証拠の信憑性、裁判官の判断なども影響します。実際に、法律上は「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。」(民法770条2項)と規定されており、裁判所が離婚請求を棄却することも可能です。
もっとも、お互い離婚の意思が固まっているというケースでは、慰謝料や財産分与、親権での争いとなるため、最終的には判決ではなく和解で決着するということもありえます。基本的に、裁判離婚が成立するのは、法律上の離婚原因の存在を証拠によって立証できた場合となります。
このように、裁判離婚で必ず離婚できるわけではありません。離婚原因があるかどうかが前提となるからです。しかし、相手も離婚を望んでいる場合は、裁判所も離婚を認める方向で判断する可能性は相当程度あるといえるでしょう。 -
(3)判決が出れば離婚が成立する?
では、無事離婚が認められる判決が出た場合、離婚の手続きを踏まなくとも、そのまま離婚が成立するのでしょうか。
実は、判決が出てもそのまま自動的に離婚成立というわけではありません。第一審の判決が出た後、2週間は控訴することができるからです。この期間中に不服申し立てがなければ、控訴期間が満了します。控訴期間が過ぎると無事、判決が確定されます。
判決の確定が決まると、次は離婚の手続きが必要となります。具体的には、判決が確定した後、10日以内に以下の書類を、本籍地か住所地の市役所に届け出なければなりません。
① 判決書の謄本
② 判決確定証明書
③ 離婚届
仮にこれを忘れてしまった場合は、過料が科せられる可能性がありますので注意してください。相手方が届け出をしたがらない場合は、自ら届け出を行うようにしましょう。
2、裁判離婚の流れと裁判離婚にかかる期間
次は、離婚裁判に必要な書類や一般的な流れ、必要な期間をみていきましょう。
-
(1)離婚裁判の流れ
まずは、訴える側(原告)が訴状を提出します。これに応じて、相手方(被告)は答弁書を提出することになります。
訴状提出の約1か月後に、第一回口頭弁論が開かれます。ここでは、双方の主張となる書面や証拠が提出されます。それぞれの主張を整理した後で、原告の証拠提出、被告の証拠提出という流れになります。第一回口頭弁論が終わると、月に1回程度のペースで第二回、第三回と口頭弁論が開かれることになります。
第二回目の口頭弁論以降は、双方が主張する内容を記した書面の陳述、証拠(書証)の提出、証人尋問、本人尋問などを行います。基本的には文書のみのやりとりです。これらが全て終わったら、判決が下されます。
判決では、離婚を認容するか、棄却するかの二者択一の結論が述べられます。もっとも、裁判自体の終結の形には、判決だけではなく、原告の訴えの取り下げや和解などもありえます。訴えの取り下げについては相手方の準備書面提出後は、相手方の同意が必要です。 -
(2)離婚裁判にかかる期間
離婚裁判にかかる期間は個別の事情によるものの、一般的には1~2年程度のケースが多いでしょう。口頭弁論がだいたい月に1回あり、これらが数度繰り返され早ければ1年以内に終結することもあります。
ただし、証拠を準備するのに時間がかかったり、争点が多かったりする場合には、訴訟も長期化する傾向にあります。仮に一審で終わらず、控訴しさらに上告するようなことがあれば、3年程度かかる可能性もあります。
もっとも、そこまで長引くことはそれほど多くないため、1年程度を目安として考えてよいでしょう。お互いの妥協点を探りながら、早期解決を目指し新しい生活を始めていくことも大切です。 -
(3)離婚裁判に必要な書類
離婚裁判をする場合、必要になるのは主に以下の4つの書類です。
① 2通の訴状
② 夫婦関係調整事件不成立調書
③ 夫婦の戸籍謄本およびそのコピー
④ 源泉徴収票や預金通帳などの証拠とする書類のコピー 2部
②について、裁判離婚は調停前置主義が原則となっているため、調停不成立であったことを証明する書類として必要になります。年金分割における、按分割合(分割割合)に関する処分の申立てを同時にする場合は、「年金分割のための情報通知書およびそのコピー」も必要です。
3、離婚裁判にかかる費用の内訳と相場
次は、裁判離婚にかかる費用の種類や相場について解説します。
-
(1)裁判離婚にかかる費用の種類
裁判離婚にかかる費用は主に次の2つです。
① 裁判所費用
② 弁護士費用
裁判所費用とは、裁判所に支払う手続き費用で、必ず発生します。
弁護士費用とは、弁護士に裁判離婚の代理人をお願いするためにかかる費用で、必須ではありません。しかし、後で説明するように弁護士に任せる方が、より手続きがスムーズに進むなどのメリットがあります。 -
(2)裁判所費用の相場
離婚裁判は、裁判官の判断を仰ぐ形式の手続きになりますので、裁判所に訴え提起の手続き費用を支払う必要があります。具体的には、収入印紙や郵便切手としての費用がかかることになります。
収入印紙代は、離婚のみを求める場合で1万3000円となります。もっとも、これだけを求めるケースは少なく、財産分与や養育費についても同時に訴えを提起する場合には各項目ごとに1200円が加算されます。また、慰謝料請求も同時に行う場合は、請求額に応じた手数料が別途かかってきます。
郵便切手代については、裁判所によって金額が異なりますが、数1000円程度はかかると考えておきましょう。 -
(3)弁護士費用の相場
弁護士費用としては、基本的に以下の4つが費用としてかかります。
① 相談料
② 着手金
③ 基本報酬
④ 成功報酬
これ以外にも実費や慰謝料、財産分与などの項目ごとに、費用がかかると考えておけばよいでしょう。
ベリーベスト法律事務所にご依頼いただいた場合の費用は、『弁護士費用』のページで詳しく紹介しておりますので、ご確認ください。
お問い合わせください。
4、離婚を早期に成立させるポイント
離婚を早期に成立させるために押さえておくべきポイントを見ていきましょう。
-
(1)確実な証拠を手に入れておく
早期解決を実現するためには、あなたの主張が認められるように論理的に展開していかなければいけません。そのためには、証拠が必要不可欠です。離婚原因があることを証明する客観的事実があれば、争点が減り早期解決が望めます。
たとえば、DVを受けていたのであれば医師の診断書が証拠になります。暴言を繰り返し受けたというケースであれば、その事実が書かれた日記なども証拠となります。これ以外にも、不倫の決定的な証拠や精神的苦痛があったのであれば通院歴などの記録・費用の領収書なども証拠となります。
法律上の離婚原因にあてはまる事由につき、できるだけ多くの証拠を集めることで、裁判官は判断を行いやすくなります。裁判が始まる前にできる限りの証拠を集めておきましょう。
弁護士に相談すれば、個別のケースごとに必要な証拠や集め方をアドバイスしてくれます。 -
(2)裁判までに争点をはっきりさせておく
争いのない部分は、先に両者の話し合いによりまとめておくことも大切です。裁判までに争点をはっきりさせておくことで、裁判の早期終結がかないます。
子どもの親権や養育費について裁判上の争点となることは少なくありません。子どもの親権者については、どちらかに決めないと離婚届が受理されない仕組みとなっているため、可能であるならば、子どもにとって夫婦どちらが親権を持つのが適切かについて話し合っておきましょう。難しい決断となりますので、話がまとまらない場合は、裁判で争うこともやむなしとなります。
このように、裁判で争点となりそうなことを裁判までに話し合いでまとめておくことが早期解決への重要なプロセスとなります。妥協できないこともありますが、早期解決を望むなら争点を絞ったうえで裁判に臨むことも必要です。
5、経験豊富な弁護士に依頼するメリットは?
最後に、弁護士に依頼するメリットについて見ていきましょう。
-
(1)裁判手続きが円滑に進む
弁護士は法律の専門家です。離婚裁判において、どのように手続きを進めればよいかを熟知しているだけでなく、裁判書類作成などの手続きも任せることができるため、当事者は安心して裁判を迎えることができます。
また、依頼人の主張が通りやすくなるよう論理的に主張を組み立てることができます。特に、離婚裁判について経験豊富な弁護士であれば、さまざまなケースを扱っているため、個別ケースに応じて対策を講じることができるでしょう。 -
(2)親権や財産分与についてポイントを押さえて主張できる
弁護士がついていれば、絶対勝てるというものではありません。しかし、裁判においてどんなポイントをおさえて主張すれば、親権や財産分与の主張が認められやすいのかは熟知しています。
そのため、法律を知らない当事者が主張するよりも、効果的に主張を展開することが可能となるのです。仮に、相手方に弁護士がついている場合には、法律のプロを相手に当事者本人だけで効果的に主張・反論していくのは困難であるため、こちらも弁護士に依頼したほうがよいでしょう。 -
(3)早期解決が望める
弁護士に依頼することで裁判が円滑に進むため、早期解決を望めます。あなたの主張が通りやすいようアドバイスも行ってくれるため、どの程度で折り合いをつけるべきかの判断などもやりやすくなるはずです。
お問い合わせください。
6、まとめ
裁判で離婚が認められるには民法上の離婚原因が必要であり、裁判をすれば必ずしも離婚できるとは限りません。また、裁判においては離婚原因を証明する証拠集めや、主張を論理的に展開することが重要となるため、弁護士への依頼がおすすめです。
弁護士に依頼すると費用がかかるため、躊躇してしまうという方も多いでしょう。しかし、できるだけ早い解決を望む場合は、経験豊富な専門家である弁護士に任せることをおすすめします。離婚成立まで全力でサポートしますので、ベリーベスト法律事務所 那覇オフィスの弁護士までお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています